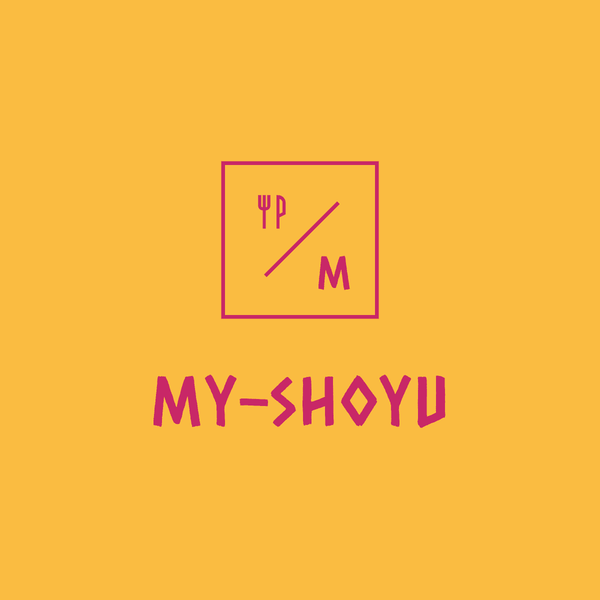醤油はソイソースとして世界に広まっているのは知られるところ。
ソイ(Soy): 大豆 だから大豆のソースという意味である。
英語ではSoyだが、スペイン語ではSoyaという。英語のソース(sauce)はスペイン語ではサルサ(salsa)となるので、ソイソース(Soy sauce)はサルサ・デ・ソヤ(Salsa de soya)となる。これも大豆のソース。
ところが話はややこしくて、英語でも結構Soyaを使うケースが多い印象がある。
その場合、ソヤソースとなる訳である。例えば食品産業ではレシチンという原料が多く使われるが、大豆由来のものはソイレシチンもソヤレシチンも混在している。
別に話をしていても、文面を読んでいてもそのまま流れるので支障はないものの、どっちが正しいのか、どっちがよく使われるのかと立ち止まってしまうときがある。
よく知られるところでは、日本の「ショウユ・Shoyu」が「ソヤ・Soya」となり、「ソイ・Soy」に至ったということだが直感的に分かりやすい。
大豆ありきで言葉がつながったのではなく、醤油が語源となっているのであれば、醤油が文化をつなぐ橋渡しをしたともいえる。
そんなことを考えてませんでしたが、タイの食料品店にも醤油がたくさんあるなと思いながら眺めていました。
日本語表記・輸出品と日本以外で製造した英語表記のものが混在しているのも、国際的な雰囲気を感じる一面です。