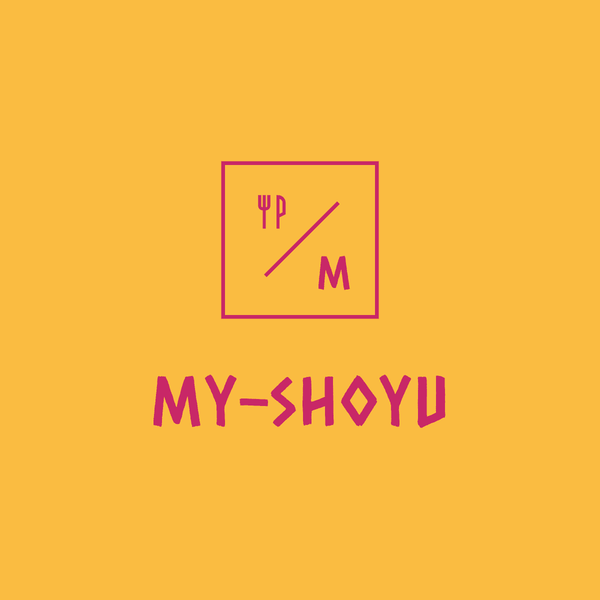2019年1月、ポン菓子に雲南省の山奥で遭遇した。
*いま改めて調べると紅河県金平ミャオ族ヤオ族タイ族自治県の老勐郷というところの少数民族のバザールだったよう。
「ぱっかん」というのが子供の時に覚えた名称だけど三重県だけなのか?幼少時に住んでたところの比較的近くのお店が一番にヒットした。
http://pongasi.my.land.to/iikata.htm
https://chubum.base.shop/items/65555904
子どものころ家の前に軽トラックのおっちゃんが来て、米と砂糖と100円(だったかな?)で作ってもらったけど、うちの砂糖は茶色くてなんだか気恥ずかしかったのを覚えている。
さてよく知られるように雲南省は米、茶があり、日本と同じ照葉樹林文化である。
米の料理は粒以外にも米線、米粉と多岐に亘っている。シナ北部に行くと米銭と書くのは米線と同じ発音だから入れ替わったという中国語のよくあるパターンだと思う。
余談ついでながら、米のヌードルは麺とは書かない。麺=麦+面だから、すなわち小麦を使ったものを言い(しかも現代語は面と書く)、縛りがあるというのが中国の友人・張さんの力説。
だから蕎麦なんかも同じ。そういえば江戸時代に現代のような蕎麦ヌードルが開発されたときは蕎麦切りって言ってたみたいだから、その頃は同じ感覚かも知れない。
今の日本ではヌードルのことをほとんど麺というけど、逆に中華そばとか志那そばという戦後の言葉ではヌードルをそばと言うこともありほとんどカオスである。
中国に戻るとパスタ、特にスパゲティのことだと思うけど伊太利面という。たしかに小麦粉で、ここはやはり漢字の国だと感心するし、一方で日本人感覚では違和感もある。
日本の漢字、カナのミックスもやはり文化だと感心することが多い。
脱線が過ぎました。
雲南も米文化だから似たようなものがあって当然という話しながら、ポン菓子はもっと多様。
米の種類も色もおそらく多様だし、それ以外のキビのような穀類や豆も使ってあり、いろいろミックスとか薄いシート状に固めたものとか多彩。
ただ元々どうやって膨らませているのかは不明。揚げてるのかな?



2種類袋詰めしてもらってゲストハウスで食べてました。
あまり豪州や米国の人のウケはよくなかったけど、最近はヨーロッパでも似たようなものを見かける。
いろんな雑穀で作れば栄養価のオプションも楽しみも広がっていい。
こういうのも米の利用を広げるいいアイデアだと思う。