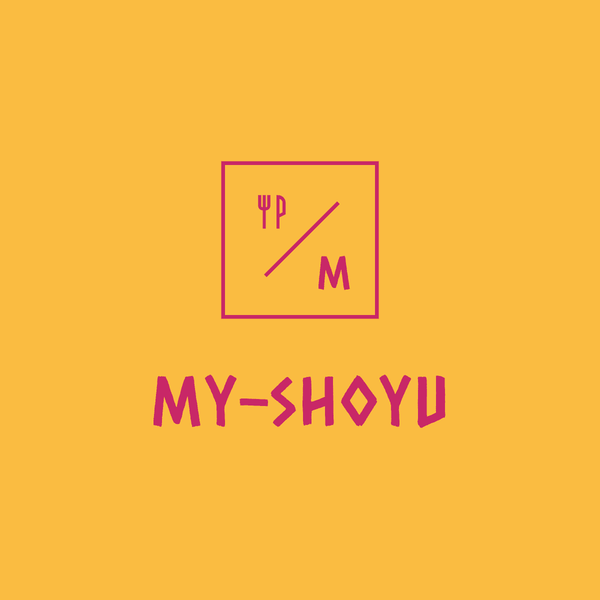ポン菓子を見つけた雲南の田舎の市場について少し触れたので思い出していました。
中国の辺境と言えば新疆ウイグル自治区エリアのトルコ系のウイグル族やカザフ族、キルギス族などの民族が催すバザールに行ったことがある。
この雲南の市場に行ってバザールという言葉を思い出したのだが、何か言い方があるのだろうか。市場、でいいのか?
雲南に行った目的はいくつかあったのだが、その一つが棚田を見に行くこと。

その日も夜明け前に起きて眺めていたのだが、市場に行くから一緒に行くかと聞かれ、同行することにした。
山を越え、谷を越え、でどこに向かっているのかわからなかったが、最終的にいたのは紅河県金平ミャオ族ヤオ族タイ族自治県の老勐郷。


渋滞にはまってしばらく動けなかったところ、降りて歩いて行ってくれと。
Googleマップが使えない国ではMAPS.MEという地図Appを使う。

たどり着いたそれらしいところはあまり人がいない。






見たこともない煙管を楽しむ人がいると思ったら売られていたので、それなりに流通しているよう。

練炭もあちこちで見かけた。
煮炊きをするのはガスではなくて炭なのかも知れない。

と、そんなガスもない生活でありながらも決済は皆がWeChatペイかアリペイ。
少なくとも現金で支払っているのは自分だけしか見なかった。
偽札なども含めて現金の信用力がないなどの事情はさておき、こういうシーンに出くわすと日本のキャッシュレス化の遅れが際立って目立つ。
2024年5月現在、新紙幣が7月に導入されることが一部ニュースになっているが、この市場訪問は2019年1月のこと。しかもほとんどが青空市場。そこでの決済が全てQRコード利用。考えざるを得ない。


空いてるな、と思っていたが気付けば人だらけ。単に時間が早かっただけのよう。



まな板と料理包丁を見ると、同じ東アジア文化で共通する要素もありながらも日中の差が対照的。
あちらでは重たい鉈(ナタ)のような刃でぶった切る。だからまな板もそれに対抗するように年輪が見えるような向きの作り。


この差は戦闘時の刀にもあるようですね。骨までぶった切るようなスタイルに対して、日本刀は研ぎ澄ましたような切れ味。
お酒でいうと、何もかもを溶かし込んだ老練な老酒に対して、磨き上げた清廉な味が特徴の日本酒。あくまでも典型的なものとしては、ということですが。

たくさん買い出しに来ていました。
これまでも新鮮な鶏を求める人向けに生きてる鶏を売ってるシーンや、西の方では生きてる羊の取引なんかを見てきたけど、ここではかわいい子ブタちゃんが連れられていった。
きっと味も抜群なことでしょう。
実際に日本の街で生活しているとそういうシーンに出くわすことはなく、命をいただいているという実感が湧かない。
ここではまだ命と食の感覚が直結している。

市場をでたところでは車の窓の上に米。糒(乾飯・ほしいい)?

とりあえず帰る事になったものの、やはり渋滞で車がいつまで経っても来ない。
このままここに残されたらどこか泊まるところあるのか?と思いながら、のんびり日向ぼっこをしていたあの日。