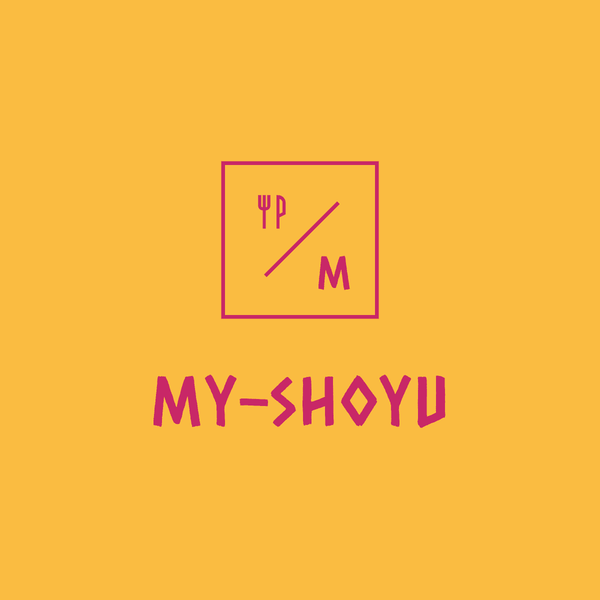コラム

干しブドウ
2006年10月 トルコ・パムッカレにて 道端のおばちゃんに干しブドウを分けてもらいました。 ただ干していたものを回収していただけなのか、それとも販売していたのか、また買ったのか、タダで分けてもらったのかも含めて記憶が定かではありません。 乾燥する地域でブドウがたくさん取れて、さらに乾きやすいから簡単にできそう。 というより路上に放置されていたかのよう。
干しブドウ
2006年10月 トルコ・パムッカレにて 道端のおばちゃんに干しブドウを分けてもらいました。 ただ干していたものを回収していただけなのか、それとも販売していたのか、また買ったのか、タダで分けてもらったのかも含めて記憶が定かではありません。 乾燥する地域でブドウがたくさん取れて、さらに乾きやすいから簡単にできそう。 というより路上に放置されていたかのよう。

アイルランドの市場で見かけた醤油
アイルランド南部にある第2の都市Cork(コーク)。 ここでローカルの市場に足を延ばしました。その名も”English Market”https://www.corkcity.ie/en/english-market/ 肉やら魚やらいろんな専門店があった中、アジア食材店も。 当然醬油もたくさんありました。 KIKKOMANがやはり高級ブランドです。 一般に中国製は安価。 KEJAP MANIS(ケチャップマニス)はインドネシアの大豆発酵調味料、つまり醤油かどうかは別としてSoy sauce。 ちなみにケチャップイカンというのは魚醤ですが、ケチャップという言葉にソースの意味合いがあるようです。元々は中国南方からの華僑が使う言葉から来ているようです。 このケチャップが伝わって、あるところではトマトが使われ、私たちがよく目にするものになり、欧州ではマッシュルームのケチャップなんかがあります。 ※トップの写真は現場で撮っただけで記事とは関係ありません。(ライ麦パン、買って帰りましたけど)
アイルランドの市場で見かけた醤油
アイルランド南部にある第2の都市Cork(コーク)。 ここでローカルの市場に足を延ばしました。その名も”English Market”https://www.corkcity.ie/en/english-market/ 肉やら魚やらいろんな専門店があった中、アジア食材店も。 当然醬油もたくさんありました。 KIKKOMANがやはり高級ブランドです。 一般に中国製は安価。 KEJAP MANIS(ケチャップマニス)はインドネシアの大豆発酵調味料、つまり醤油かどうかは別としてSoy sauce。 ちなみにケチャップイカンというのは魚醤ですが、ケチャップという言葉にソースの意味合いがあるようです。元々は中国南方からの華僑が使う言葉から来ているようです。 このケチャップが伝わって、あるところではトマトが使われ、私たちがよく目にするものになり、欧州ではマッシュルームのケチャップなんかがあります。 ※トップの写真は現場で撮っただけで記事とは関係ありません。(ライ麦パン、買って帰りましたけど)
柚餅子
2022年初冬の日にクラウドファンディングで調べごとをしていた折に、古民家で柚餅子づくりという企画を見つけ参加してみました。 藤野薬膳柚餅子づくり 場所は神奈川県相模原市の藤野。山梨県の手前です。アーティストが住んだり、外国人の人にも古き良き日本の雰囲気で人気のところ。 私にとっては山歩きをする際のアクセスする麓の集落ですが、一般には中央道から見えるラブレターが知られているかも知れません。 ということで築200年だか300年もする立派な古民家へ。 そもそも日本家屋好きで伝統工法に思い入れがある身としては、すでにテンションが上がってます。 いまは神奈川県でここから山を越えた次の谷は山梨県。でも武田家の縄張り範囲だったんでしょうね。 まずは急斜面の柚子畑に収穫へ。 畑で育っている金柑もそうですが、同じ柑橘のこの柚子も枝の棘(トゲ)が危険です。 みかん、レモン、グレープフルーツ・・・何気なく楽しんでいる果実も、そういう棘がある中を収穫された苦労の賜物なんでしょう。 上部をカットし、果肉を取り出す。 そしていろいろな中身を準備。えらくご丁寧な品揃えでした。 八丁味噌と混ぜる。 そして詰める。 その後、蓋をして蒸籠で蒸して、2ヵ月風乾・熟成。 しばらく物干し竿を占領していました。味噌の色が染み出てきて、柚子の皮も黒く染まる。 そして出来上がったものをスライスして食べる! これがうまい。お酒のつまみにも、ということだけど我が家では朝食の添え物がメイン、たまに熱湯を注いでお茶漬け。 柚餅子(ゆべし)というと和菓子を思い浮かべていたのだけど、八丁味噌ベースのこちらは食事に合わせてぴったり。 なぜ同じ柚餅子という言葉で別のものが存在するのか調べていませんが、いま柚餅子と聞くとこちらの柚子と味噌を使った保存食を思い出します。 調べてみると、なんと三重県の親元の近所の醸造所で製造販売している。 独自の進化で濃厚な珍味に…間もなく出荷の『伊勢ゆべし』は“酒のつまみ”にぴったり しかも、醸造所の名前が母親の旧姓だし、原料の柚子は父親の故郷のものだし、不思議な縁も。 地元でそんなのあるなんて知らなかった。聞いてみたら母親は自分で作っていたらしいけど。見たことなかったな。たぶん興味がなかった、その頃は。 イベントに参加した息子は思い入れがあるからなのか、初めから食べている。いまではどうも好物のレベルの様子。 なんてことがありながら昨年の冬。...
柚餅子
2022年初冬の日にクラウドファンディングで調べごとをしていた折に、古民家で柚餅子づくりという企画を見つけ参加してみました。 藤野薬膳柚餅子づくり 場所は神奈川県相模原市の藤野。山梨県の手前です。アーティストが住んだり、外国人の人にも古き良き日本の雰囲気で人気のところ。 私にとっては山歩きをする際のアクセスする麓の集落ですが、一般には中央道から見えるラブレターが知られているかも知れません。 ということで築200年だか300年もする立派な古民家へ。 そもそも日本家屋好きで伝統工法に思い入れがある身としては、すでにテンションが上がってます。 いまは神奈川県でここから山を越えた次の谷は山梨県。でも武田家の縄張り範囲だったんでしょうね。 まずは急斜面の柚子畑に収穫へ。 畑で育っている金柑もそうですが、同じ柑橘のこの柚子も枝の棘(トゲ)が危険です。 みかん、レモン、グレープフルーツ・・・何気なく楽しんでいる果実も、そういう棘がある中を収穫された苦労の賜物なんでしょう。 上部をカットし、果肉を取り出す。 そしていろいろな中身を準備。えらくご丁寧な品揃えでした。 八丁味噌と混ぜる。 そして詰める。 その後、蓋をして蒸籠で蒸して、2ヵ月風乾・熟成。 しばらく物干し竿を占領していました。味噌の色が染み出てきて、柚子の皮も黒く染まる。 そして出来上がったものをスライスして食べる! これがうまい。お酒のつまみにも、ということだけど我が家では朝食の添え物がメイン、たまに熱湯を注いでお茶漬け。 柚餅子(ゆべし)というと和菓子を思い浮かべていたのだけど、八丁味噌ベースのこちらは食事に合わせてぴったり。 なぜ同じ柚餅子という言葉で別のものが存在するのか調べていませんが、いま柚餅子と聞くとこちらの柚子と味噌を使った保存食を思い出します。 調べてみると、なんと三重県の親元の近所の醸造所で製造販売している。 独自の進化で濃厚な珍味に…間もなく出荷の『伊勢ゆべし』は“酒のつまみ”にぴったり しかも、醸造所の名前が母親の旧姓だし、原料の柚子は父親の故郷のものだし、不思議な縁も。 地元でそんなのあるなんて知らなかった。聞いてみたら母親は自分で作っていたらしいけど。見たことなかったな。たぶん興味がなかった、その頃は。 イベントに参加した息子は思い入れがあるからなのか、初めから食べている。いまではどうも好物のレベルの様子。 なんてことがありながら昨年の冬。...
雲南の市場
ポン菓子を見つけた雲南の田舎の市場について少し触れたので思い出していました。 中国の辺境と言えば新疆ウイグル自治区エリアのトルコ系のウイグル族やカザフ族、キルギス族などの民族が催すバザールに行ったことがある。 この雲南の市場に行ってバザールという言葉を思い出したのだが、何か言い方があるのだろうか。市場、でいいのか? 雲南に行った目的はいくつかあったのだが、その一つが棚田を見に行くこと。 その日も夜明け前に起きて眺めていたのだが、市場に行くから一緒に行くかと聞かれ、同行することにした。 山を越え、谷を越え、でどこに向かっているのかわからなかったが、最終的にいたのは紅河県金平ミャオ族ヤオ族タイ族自治県の老勐郷。 渋滞にはまってしばらく動けなかったところ、降りて歩いて行ってくれと。 Googleマップが使えない国ではMAPS.MEという地図Appを使う。 たどり着いたそれらしいところはあまり人がいない。 見たこともない煙管を楽しむ人がいると思ったら売られていたので、それなりに流通しているよう。 練炭もあちこちで見かけた。 煮炊きをするのはガスではなくて炭なのかも知れない。 と、そんなガスもない生活でありながらも決済は皆がWeChatペイかアリペイ。 少なくとも現金で支払っているのは自分だけしか見なかった。 偽札なども含めて現金の信用力がないなどの事情はさておき、こういうシーンに出くわすと日本のキャッシュレス化の遅れが際立って目立つ。 2024年5月現在、新紙幣が7月に導入されることが一部ニュースになっているが、この市場訪問は2019年1月のこと。しかもほとんどが青空市場。そこでの決済が全てQRコード利用。考えざるを得ない。 空いてるな、と思っていたが気付けば人だらけ。単に時間が早かっただけのよう。 まな板と料理包丁を見ると、同じ東アジア文化で共通する要素もありながらも日中の差が対照的。 あちらでは重たい鉈(ナタ)のような刃でぶった切る。だからまな板もそれに対抗するように年輪が見えるような向きの作り。 この差は戦闘時の刀にもあるようですね。骨までぶった切るようなスタイルに対して、日本刀は研ぎ澄ましたような切れ味。 お酒でいうと、何もかもを溶かし込んだ老練な老酒に対して、磨き上げた清廉な味が特徴の日本酒。あくまでも典型的なものとしては、ということですが。 たくさん買い出しに来ていました。 これまでも新鮮な鶏を求める人向けに生きてる鶏を売ってるシーンや、西の方では生きてる羊の取引なんかを見てきたけど、ここではかわいい子ブタちゃんが連れられていった。 きっと味も抜群なことでしょう。 実際に日本の街で生活しているとそういうシーンに出くわすことはなく、命をいただいているという実感が湧かない。...
雲南の市場
ポン菓子を見つけた雲南の田舎の市場について少し触れたので思い出していました。 中国の辺境と言えば新疆ウイグル自治区エリアのトルコ系のウイグル族やカザフ族、キルギス族などの民族が催すバザールに行ったことがある。 この雲南の市場に行ってバザールという言葉を思い出したのだが、何か言い方があるのだろうか。市場、でいいのか? 雲南に行った目的はいくつかあったのだが、その一つが棚田を見に行くこと。 その日も夜明け前に起きて眺めていたのだが、市場に行くから一緒に行くかと聞かれ、同行することにした。 山を越え、谷を越え、でどこに向かっているのかわからなかったが、最終的にいたのは紅河県金平ミャオ族ヤオ族タイ族自治県の老勐郷。 渋滞にはまってしばらく動けなかったところ、降りて歩いて行ってくれと。 Googleマップが使えない国ではMAPS.MEという地図Appを使う。 たどり着いたそれらしいところはあまり人がいない。 見たこともない煙管を楽しむ人がいると思ったら売られていたので、それなりに流通しているよう。 練炭もあちこちで見かけた。 煮炊きをするのはガスではなくて炭なのかも知れない。 と、そんなガスもない生活でありながらも決済は皆がWeChatペイかアリペイ。 少なくとも現金で支払っているのは自分だけしか見なかった。 偽札なども含めて現金の信用力がないなどの事情はさておき、こういうシーンに出くわすと日本のキャッシュレス化の遅れが際立って目立つ。 2024年5月現在、新紙幣が7月に導入されることが一部ニュースになっているが、この市場訪問は2019年1月のこと。しかもほとんどが青空市場。そこでの決済が全てQRコード利用。考えざるを得ない。 空いてるな、と思っていたが気付けば人だらけ。単に時間が早かっただけのよう。 まな板と料理包丁を見ると、同じ東アジア文化で共通する要素もありながらも日中の差が対照的。 あちらでは重たい鉈(ナタ)のような刃でぶった切る。だからまな板もそれに対抗するように年輪が見えるような向きの作り。 この差は戦闘時の刀にもあるようですね。骨までぶった切るようなスタイルに対して、日本刀は研ぎ澄ましたような切れ味。 お酒でいうと、何もかもを溶かし込んだ老練な老酒に対して、磨き上げた清廉な味が特徴の日本酒。あくまでも典型的なものとしては、ということですが。 たくさん買い出しに来ていました。 これまでも新鮮な鶏を求める人向けに生きてる鶏を売ってるシーンや、西の方では生きてる羊の取引なんかを見てきたけど、ここではかわいい子ブタちゃんが連れられていった。 きっと味も抜群なことでしょう。 実際に日本の街で生活しているとそういうシーンに出くわすことはなく、命をいただいているという実感が湧かない。...

雲南のポン菓子
2019年1月、ポン菓子に雲南省の山奥で遭遇した。 *いま改めて調べると紅河県金平ミャオ族ヤオ族タイ族自治県の老勐郷というところの少数民族のバザールだったよう。 「ぱっかん」というのが子供の時に覚えた名称だけど三重県だけなのか?幼少時に住んでたところの比較的近くのお店が一番にヒットした。 http://pongasi.my.land.to/iikata.htm https://chubum.base.shop/items/65555904 子どものころ家の前に軽トラックのおっちゃんが来て、米と砂糖と100円(だったかな?)で作ってもらったけど、うちの砂糖は茶色くてなんだか気恥ずかしかったのを覚えている。 さてよく知られるように雲南省は米、茶があり、日本と同じ照葉樹林文化である。 米の料理は粒以外にも米線、米粉と多岐に亘っている。シナ北部に行くと米銭と書くのは米線と同じ発音だから入れ替わったという中国語のよくあるパターンだと思う。 余談ついでながら、米のヌードルは麺とは書かない。麺=麦+面だから、すなわち小麦を使ったものを言い(しかも現代語は面と書く)、縛りがあるというのが中国の友人・張さんの力説。 だから蕎麦なんかも同じ。そういえば江戸時代に現代のような蕎麦ヌードルが開発されたときは蕎麦切りって言ってたみたいだから、その頃は同じ感覚かも知れない。 今の日本ではヌードルのことをほとんど麺というけど、逆に中華そばとか志那そばという戦後の言葉ではヌードルをそばと言うこともありほとんどカオスである。 中国に戻るとパスタ、特にスパゲティのことだと思うけど伊太利面という。たしかに小麦粉で、ここはやはり漢字の国だと感心するし、一方で日本人感覚では違和感もある。 日本の漢字、カナのミックスもやはり文化だと感心することが多い。 脱線が過ぎました。 雲南も米文化だから似たようなものがあって当然という話しながら、ポン菓子はもっと多様。 米の種類も色もおそらく多様だし、それ以外のキビのような穀類や豆も使ってあり、いろいろミックスとか薄いシート状に固めたものとか多彩。 ただ元々どうやって膨らませているのかは不明。揚げてるのかな? 2種類袋詰めしてもらってゲストハウスで食べてました。 あまり豪州や米国の人のウケはよくなかったけど、最近はヨーロッパでも似たようなものを見かける。 いろんな雑穀で作れば栄養価のオプションも楽しみも広がっていい。 こういうのも米の利用を広げるいいアイデアだと思う。
雲南のポン菓子
2019年1月、ポン菓子に雲南省の山奥で遭遇した。 *いま改めて調べると紅河県金平ミャオ族ヤオ族タイ族自治県の老勐郷というところの少数民族のバザールだったよう。 「ぱっかん」というのが子供の時に覚えた名称だけど三重県だけなのか?幼少時に住んでたところの比較的近くのお店が一番にヒットした。 http://pongasi.my.land.to/iikata.htm https://chubum.base.shop/items/65555904 子どものころ家の前に軽トラックのおっちゃんが来て、米と砂糖と100円(だったかな?)で作ってもらったけど、うちの砂糖は茶色くてなんだか気恥ずかしかったのを覚えている。 さてよく知られるように雲南省は米、茶があり、日本と同じ照葉樹林文化である。 米の料理は粒以外にも米線、米粉と多岐に亘っている。シナ北部に行くと米銭と書くのは米線と同じ発音だから入れ替わったという中国語のよくあるパターンだと思う。 余談ついでながら、米のヌードルは麺とは書かない。麺=麦+面だから、すなわち小麦を使ったものを言い(しかも現代語は面と書く)、縛りがあるというのが中国の友人・張さんの力説。 だから蕎麦なんかも同じ。そういえば江戸時代に現代のような蕎麦ヌードルが開発されたときは蕎麦切りって言ってたみたいだから、その頃は同じ感覚かも知れない。 今の日本ではヌードルのことをほとんど麺というけど、逆に中華そばとか志那そばという戦後の言葉ではヌードルをそばと言うこともありほとんどカオスである。 中国に戻るとパスタ、特にスパゲティのことだと思うけど伊太利面という。たしかに小麦粉で、ここはやはり漢字の国だと感心するし、一方で日本人感覚では違和感もある。 日本の漢字、カナのミックスもやはり文化だと感心することが多い。 脱線が過ぎました。 雲南も米文化だから似たようなものがあって当然という話しながら、ポン菓子はもっと多様。 米の種類も色もおそらく多様だし、それ以外のキビのような穀類や豆も使ってあり、いろいろミックスとか薄いシート状に固めたものとか多彩。 ただ元々どうやって膨らませているのかは不明。揚げてるのかな? 2種類袋詰めしてもらってゲストハウスで食べてました。 あまり豪州や米国の人のウケはよくなかったけど、最近はヨーロッパでも似たようなものを見かける。 いろんな雑穀で作れば栄養価のオプションも楽しみも広がっていい。 こういうのも米の利用を広げるいいアイデアだと思う。

春のある日
4月のこと。春のある休日の朝、近所の市場へ。 野菜売り場にタケノコとワラビを発見。手抜き心からタケノコはつい茹でてあったものをチョイス。 その後畑に行くと、畑の土地の所有者さんからはタラの芽持ってって、とゴソッと渡される。 実は市場で春の食材に大興奮して、あれやこれやと買っていたため、頭の中は数日分あれを食べてこれを食べてと考えていた。でも嬉しい誤算。 ホタルイカは初挑戦の炊き込みご飯。 タラの芽は天ぷらに。結構開いているけど、それもまたうまい。 タケノコ、メヒカリは天ぷらに。 そして茹でたこ1匹は刺身にたこ焼きに、で翌日残り物を炊き込みご飯に。 このときは連日、ホタルイカご飯、タコご飯、タケノコご飯と満足飯シリーズでした。
春のある日
4月のこと。春のある休日の朝、近所の市場へ。 野菜売り場にタケノコとワラビを発見。手抜き心からタケノコはつい茹でてあったものをチョイス。 その後畑に行くと、畑の土地の所有者さんからはタラの芽持ってって、とゴソッと渡される。 実は市場で春の食材に大興奮して、あれやこれやと買っていたため、頭の中は数日分あれを食べてこれを食べてと考えていた。でも嬉しい誤算。 ホタルイカは初挑戦の炊き込みご飯。 タラの芽は天ぷらに。結構開いているけど、それもまたうまい。 タケノコ、メヒカリは天ぷらに。 そして茹でたこ1匹は刺身にたこ焼きに、で翌日残り物を炊き込みご飯に。 このときは連日、ホタルイカご飯、タコご飯、タケノコご飯と満足飯シリーズでした。